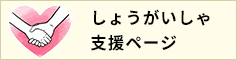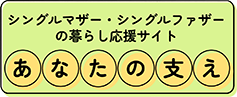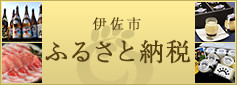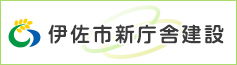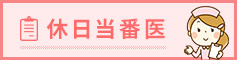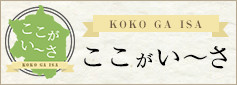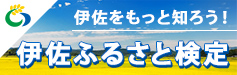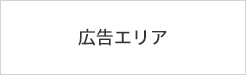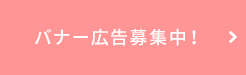“さなぶり”の効用
2014年07月01日
 先月植えられた早苗が力強く伸びて、青々とした田園風景へと変わりゆくのが七月の伊佐です。植えられた苗は頼りなく、か細く、水田に浮かんでいるような危うさでした。苗の成長は早いもので、三週間を過ぎるころにはしっかりと根を張り、風にそよぐ青々とした田園風景に変わりました。秋の黄金色が伊佐平野を代表する風景のように思う人が多いですが、さざ波のように風に揺れる青々とした田園風景の七月が、一番みずみずしく美しいと聞いたことがあります。この時期の農家は疲れを癒し、家族や友達を誘い、”さなぶり”と称して、温泉や食事・飲み会を楽しみます。
先月植えられた早苗が力強く伸びて、青々とした田園風景へと変わりゆくのが七月の伊佐です。植えられた苗は頼りなく、か細く、水田に浮かんでいるような危うさでした。苗の成長は早いもので、三週間を過ぎるころにはしっかりと根を張り、風にそよぐ青々とした田園風景に変わりました。秋の黄金色が伊佐平野を代表する風景のように思う人が多いですが、さざ波のように風に揺れる青々とした田園風景の七月が、一番みずみずしく美しいと聞いたことがあります。この時期の農家は疲れを癒し、家族や友達を誘い、”さなぶり”と称して、温泉や食事・飲み会を楽しみます。
 農事が生活の一部になっている農山村においては、このような出来事・催しが大切なコミュニケーションの場にもなっています。私の集落でも12日に青壮年会が中心になり食事会を催しますし、いくつかの集落からはご案内をいただいています。遠い昔と言われそうですが、私が小・中学生の頃は田植えはまだ機械化されておらず、早乙女(言葉としては死語となってるかなぁ~?)の手植えや”結い”で作業が行われていました。人手もかかり、体も疲れる作業だったので”さなぶり”をなによりも楽しみにして、一致団結したコミュニケーションがありました。
農事が生活の一部になっている農山村においては、このような出来事・催しが大切なコミュニケーションの場にもなっています。私の集落でも12日に青壮年会が中心になり食事会を催しますし、いくつかの集落からはご案内をいただいています。遠い昔と言われそうですが、私が小・中学生の頃は田植えはまだ機械化されておらず、早乙女(言葉としては死語となってるかなぁ~?)の手植えや”結い”で作業が行われていました。人手もかかり、体も疲れる作業だったので”さなぶり”をなによりも楽しみにして、一致団結したコミュニケーションがありました。
 本格的な梅雨の前に田植えを終わらせ、”さなぶり”で集落みんなが気持ちをひとつにします。このような一連の流れは防災対策上も重要な意味を持ちます。隣近所と一緒に過ごす時間が少ない現代における避難対策準備の場にもなります。集落内の支援が必要な高齢者や障がい者の話題も出ますし、危険個所の話題から皆で情報を共有できます。都市に出張していつも思うことは、人と人のつながりの希薄さです。駅のホームや歩きながらスマホを操作している人、エレベーターの中の沈黙、無駄話をしない会議等々・・伊佐の雰囲気とあまりにも違うことを感じます。
本格的な梅雨の前に田植えを終わらせ、”さなぶり”で集落みんなが気持ちをひとつにします。このような一連の流れは防災対策上も重要な意味を持ちます。隣近所と一緒に過ごす時間が少ない現代における避難対策準備の場にもなります。集落内の支援が必要な高齢者や障がい者の話題も出ますし、危険個所の話題から皆で情報を共有できます。都市に出張していつも思うことは、人と人のつながりの希薄さです。駅のホームや歩きながらスマホを操作している人、エレベーターの中の沈黙、無駄話をしない会議等々・・伊佐の雰囲気とあまりにも違うことを感じます。
 無駄話と言っても、それは季節の挨拶や雑談的な会話のことです。潤いや絆を大切にする社会に必要な”潤滑油”みたいなものです。災害が起きてから絆ができるようでは遅いのであって、災害が起きても起きなくても日常生活の中の当たり前のこととして、目の前の人の顔を見て、沈黙より無駄話を好むようになりたいものです。効率的な生き方が経済発展や社会の成熟によってもたらされ、自分にとってのメリット・ディメリットが価値判断のひとつなっている現代社会を見直す機会が、”さなぶり”や”夏休み”なのかもしれません。どうか伊佐平野を渡る心地よい風を忘れないでください。
無駄話と言っても、それは季節の挨拶や雑談的な会話のことです。潤いや絆を大切にする社会に必要な”潤滑油”みたいなものです。災害が起きてから絆ができるようでは遅いのであって、災害が起きても起きなくても日常生活の中の当たり前のこととして、目の前の人の顔を見て、沈黙より無駄話を好むようになりたいものです。効率的な生き方が経済発展や社会の成熟によってもたらされ、自分にとってのメリット・ディメリットが価値判断のひとつなっている現代社会を見直す機会が、”さなぶり”や”夏休み”なのかもしれません。どうか伊佐平野を渡る心地よい風を忘れないでください。
 今月に入って、早速夏休み休暇を調整している職場もあるかと思います。子どもたちも19日から夏休みが始まります。家族や友達同士で魅力ある計画が大いに立てられているのではないでしょうか。どんよりした梅雨空の後に来る青空を楽しみにしたり、大雨の時は災害が起きないように祈りにも似た気持ちにもなるでしょう。大雨や暑くてどうしようもない季節に、私たちは効率的な生き方はできません。急いだりしては怪我や事故のもとになります。こんな季節にこそ、大いなる無駄話や余裕のある時間を大切にしたいものです。
今月に入って、早速夏休み休暇を調整している職場もあるかと思います。子どもたちも19日から夏休みが始まります。家族や友達同士で魅力ある計画が大いに立てられているのではないでしょうか。どんよりした梅雨空の後に来る青空を楽しみにしたり、大雨の時は災害が起きないように祈りにも似た気持ちにもなるでしょう。大雨や暑くてどうしようもない季節に、私たちは効率的な生き方はできません。急いだりしては怪我や事故のもとになります。こんな季節にこそ、大いなる無駄話や余裕のある時間を大切にしたいものです。
26日の伊佐市夏祭りです。昼間は午後3時30分から八坂神社の神輿を先頭にパレードです。沿道からの放水を喜ぶ子どもと保護者が担ぐ神輿も数多く、とても楽しめます。夕方午後7時からは市民総手踊りで盛り上がります。踊り連は各団体や企業・病院・施設などが趣向を凝らして派手を取ります。皆さんのご参加、ご来場をお待ちしています。
来月になりますが、8月1日より車椅子バスケットボール日本代表チームが合宿のため伊佐市に来市し、3日に日本代表チームの紅白戦を市総合体育
 館でおこないます。障がい者にやさしいまちづくりを進める伊佐市であり、漫画「スラムダンク」や「リアル」の作者である井上雄彦さんのふるさとである伊佐市だからこそ取り組みました。まるで格闘技を見ているような、車椅子が激しくぶつかり合う迫力をお楽しみください。詳しくは市報7月号に特集を組んでいますのでご覧ください。市ホームページでもご覧いただけます。尚、7月31日から8月4日までのボランティアも募集していますので、同じく市報で確認してください。
館でおこないます。障がい者にやさしいまちづくりを進める伊佐市であり、漫画「スラムダンク」や「リアル」の作者である井上雄彦さんのふるさとである伊佐市だからこそ取り組みました。まるで格闘技を見ているような、車椅子が激しくぶつかり合う迫力をお楽しみください。詳しくは市報7月号に特集を組んでいますのでご覧ください。市ホームページでもご覧いただけます。尚、7月31日から8月4日までのボランティアも募集していますので、同じく市報で確認してください。
週刊ヤングジャンプ[リアル]/名古桂士
 7月は梅雨から夏休みにかけて、一年で最も豪雨災害を心配しながら、無事に梅雨が明けて暑い夏が来るのを楽しみにもしています。エルニーニョ現象が発生すると言われる今年の梅雨と夏が穏やかであることを祈りながらご挨拶といたします。
7月は梅雨から夏休みにかけて、一年で最も豪雨災害を心配しながら、無事に梅雨が明けて暑い夏が来るのを楽しみにもしています。エルニーニョ現象が発生すると言われる今年の梅雨と夏が穏やかであることを祈りながらご挨拶といたします。
祈ります梅雨に男と女あり
青田風ふるさと遠き胸の底
若衆の背中に「祭」の文字踊る
昼下がり遊ぶ蝶あり凌霄花
‘夏休み‘拓郎帰る日待ってます -新ー
- こんな時には?