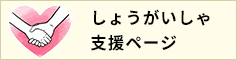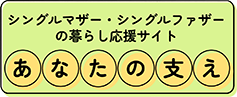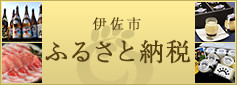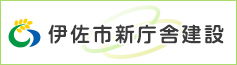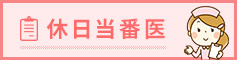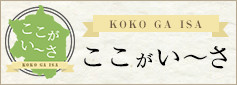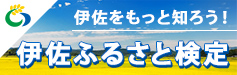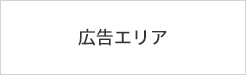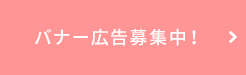保育園・児童福祉・子育て支援
保育園・児童福祉・子育て支援
- 保育園・認定こども園・幼稚園の入所申込
- 災害時における保育施設等の対応ガイドライン
- 放課後児童クラブについて
- 児童手当等について
- 児童扶養手当
- 特別児童扶養手当について
- 子ども医療費の給付について
- ひとり親家庭医療費助成制度
- 高等職業訓練促進給付金等
- 自立支援教育訓練給付金
- 母子(父子)(寡婦)福祉資金貸付事業
- 奨学金を受けたいときは
- 奨学生のみなさまへ
- 就学援助制度
- かごしま子育て支援パスポート
保育園・認定こども園・幼稚園の入所申込
入所を希望されるときは、以下のとおりに入所申込書などの配布と受付を行います。
- ⑴伊佐市内保育所・認定こども園・幼稚園
- ⑵入所できる基準
- ⑶入所申込みの受付場所・時間
- ⑷申込書の配布場所
- ⑸入所までのながれ
- ⑹保育料一覧
- ⑺ 第3子以降保育料無料化 (伊佐市独自の助成制度)
- ⑻入所申込書やその他書類のダウンロード
(1)保育園・認定こども園・幼稚園施設一覧
保育園
就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設
認定こども園
教育と保育を一体的に行う施設 幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持つ施設
幼稚園
小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校
保育園
|
園名 |
住所 |
定員 |
開所時間 |
電話番号 (0995) |
特別保育等 |
|---|---|---|---|---|---|
|
山野保育園 |
伊佐市大口山野 4275番地1 |
20 |
7時~18時 |
22-1476 |
一時預かり 延長保育 |
|
羽月保育園 |
伊佐市大口堂崎 562番地6 |
50 |
7時~18時 |
22-6388 |
一時預かり 延長保育 |
認定こども園
|
園名 |
住所 |
定員 |
開所時間 |
電話番号 (0995) |
特別保育等 (◎は他園に通園していても利用できます) |
|---|---|---|---|---|---|
|
大口幼稚園 |
伊佐市大口里 3024番地1 |
保育60 教育15 |
7時~18時 |
22-0450 |
一時預かり |
|
大口さくらこども園 |
伊佐市大口里 104番地2 |
保育 50 教育 15 |
7時~18時 |
22-8125 |
一時預かり |
|
さくらの里こども園 |
伊佐市大口大田 58番地1 |
保育 60 教育 15 |
7時~18時 |
22-2327 |
一時預かり |
|
あゆみ未来こども園 |
伊佐市大口里 2602番地 |
保育 40 教育 10 |
7時~18時 |
22-5473 |
一時預かり |
|
みどり認定こども園 |
伊佐市大口里 1842番地2 |
保育90 教育 10 |
7時~18時 |
22-2611 |
一時預かり 延長保育 休日保育(◎) |
|
ひまわり認定こども園 (みどり認定こども園 分園) |
伊佐市大口里 783番地4 |
保育 40 教育 5 |
7時~18時 |
23-5560 |
一時預かり 延長保育 |
|
こうようこども園 |
伊佐市大口曽木 1827番地1 |
保育 30 教育 5 |
7時~18時 |
25-2155 |
一時預かり |
|
明徳寺森のこども園 |
伊佐市大口元町 9番地10 |
保育 45 教育 5 |
7時~18時 |
22-6195 |
一時預かり 延長保育 |
|
認定こども園 慈光保育園 |
伊佐市菱刈前目 786番地1 |
保育 50 教育 5 |
7時30分~ 18時30分 |
26-2145 |
一時預かり 延長保育 |
|
本城こども園 |
伊佐市菱刈南浦 290番地1 |
保育 50 教育 5 |
7時30分~ 18時30分 |
26-4161 |
一時預かり 延長保育 |
|
田中認定こども園 |
伊佐市菱刈重留 1526番地2 |
保育 45 教育 10 |
7時~18時 |
26-1016 |
一時預かり 延長保育 |
|
湯之尾こども園 |
伊佐市菱刈川北 2112番地 |
保育 20 教育 5 |
7時~18時 |
26-0640 |
一時預かり 延長保育 |
幼稚園
| 園名 | 住所 | 定員 | 開所時間 | 電話番号 (0995) |
特別保育 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本城幼稚園 | 伊佐市菱刈南浦 3470番地1 |
30 |
9時~14時30分 | 26-0185 |
一時預かり
保護者の病気や急な用事で、一時的に家庭での保育ができなくなったこどもを、保育所等にてお預かりします。(園へ直接申込み)
一時預かり利用者負担軽減事業
保育所及び認定こども園が実施する一時預かり事業(任意事業を除く。)を利用した際の利用者負担額の一部を助成する制度があります。
▶詳細、様式等についてはこちら◀
延長保育
保育所等入所児童について、保護者の仕事等でお迎えが遅くなるときに保育時間の延長ができます。(園へ直接申込み)
休日保育
日曜・祝日に、お仕事の都合により家庭で保育ができない場合に、保育所等にてお預かりします。(市への事前登録が必要)
病児・病後児保育
満1歳から小学校2年生までの児童が病気の際に、保護者の仕事等で家庭での保育ができない場合、市が委託する施設にてお預かりします。(市への事前登録が必要)
| 実施施設 |
伊佐市大口里460番地1 大口さくらこども園 電話番号:080-8083-5578 |
|---|---|
| 保育時間 | 月曜日~金曜日 午前8時から午後6時まで |
| 利用料金 | 1日 1,500円 |
| 休 日 | 土・日・祝日・年末年始・施設の年度末の2日間(3月) |
病児保育の利用方法について
- こども課窓口(大口庁舎)で事前に利用登録を行います。
- 利用希望日の前日までの受付時間内に、病児保育室「ひだまり」まで、電話予約し、登録番号・児童氏名・年齢・症状等をお伝えください。
- 「利用申請書」と「診療情報提供書」が必要となります。
書類はこども課や菱刈庁舎地域総務課に準備してあります。(伊佐市ホームページや病児保育室「ひだまり」公式LINEからもダウンロードできます。)
利用する日の前日または当日の利用前までにかかりつけ医の診察を受け、「診療情報提供書」を記入していただくようお願いします。
※病児保育室「ひだまり」公式LINEについては利用登録がお済の方にお知らせいたします。 - 「利用申請書」に「診療情報提供書」を添えて、利用する日に病児保育室「ひだまり」に申請してください。
※登録後に初めて利用する際は、児童票も病児保育室「ひだまり」に提出してください。児童票は登録申請時にこども課窓口にてお渡しいたします。
申請書様式ダウンロード
- 様式第1号 伊佐市病児・病後児保育事業利用登録申請書 【Word】・【PDF】
- 様式第3号 伊佐市病児・病後児保育事業利用申請書 【Word】・【PDF】
- 様式第4号 伊佐市病児・病後児保育事業 診療情報提供書 【Word】・【PDF】
- 病児・病後児保育 児童票 【Word】・【PDF】
伊佐市病児保育利用料補助事業
病児保育を利用した際の利用者負担額一部を助成する制度があります。
詳細については「伊佐市病児保育利用料について」をご確認ください。
(2) 保育園・認定こども園(保育)へ入所できる基準
保育所等へ入所できる児童は、両親いずれも(両親と別居している場合には児童の面倒をみている人)が、次のいずれかの事情にある場合です。
- 就労(パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての就労を含む)
- 妊娠・出産(産前3か月、産後2か月)
- 保護者の疾病・障がい
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(3カ月の期限付き)
- 就学(職業訓練校等を含む)
- 育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要
- その他、虐待やDVのおそれがある等
※認定こども園(教育)・幼稚園の入所については3歳~5歳の児童はどなたでも利用できます。
(3) 受付場所・時間
保育所・認定こども園での保育認定を希望する人
|
対象者 |
場所・時間 |
|---|---|
|
全保育園及び認定こども園の 保育認定(2号・3号)希望者(市外施設を含む) |
こども課(大口庁舎) 8時30分~17時15分 |
認定こども園での教育認定を希望する人
|
対象者 |
場所・時間 |
|---|---|
|
認定こども園の 教育認定(1号)希望者 |
各認定こども園 開園時間 |
幼稚園を希望する人
| 幼稚園 | 場所・時間 |
|---|---|
| 本城幼稚園 | 教育委員会学校教育課(菱刈庁舎)8時30分~17時15分 |
※印鑑を必ずご持参ください。
(4) 申込書配布場所
- 伊佐市役所(大口庁舎)こども課
- 伊佐市役所(菱刈庁舎)地域総務課
- 伊佐市役所(菱刈庁舎)学校教育課(本城幼稚園のみ)
本ホームページからもダウンロードできます。
(5) 入所までのながれ
| ステップ(1) | 入所受付日に申込書、添付書類を提出 |
|---|---|
| ステップ(2) |
保育園の必要性・必要量を市が認定 |
| ステップ(3) | 支給認定書と入所承諾書が届き、保育所入所が決定 |
| ステップ(4) | 保育所へ入所 保育料決定通知書が届く |
(6) 保育料一覧
(7) 第3子以降保育料無料化(伊佐市独自の助成制度)
第3子以降の児童が、市内の保育園・認定こども園・幼稚園に入所すると保育料が無料になります。詳しくは「保育所・認定こども園・幼稚園入所申込み案内」に記載していますので、ご覧ください。
第3子以降の児童とは
保護者が現に養育している満18歳未満(高校3年相当)の児童のうち年長者を第1子として、年長順に数えて第3子以降の児童です。
(8) 申込書 その他様式ダウンロード
※新年度の入所申込みについては、「保育所・認定こども園・幼稚園入所申込み案内」をご覧ください。
保育園・認定こども園 入所申込み関係書類 一覧
|
№ |
書類名 |
記入例 (PDF) |
備考 |
|---|---|---|---|
|
1 |
新規申込の場合 |
||
|
2 |
継続入所の場合 |
||
|
3 |
支給認定現況届(146キロバイト/PDF) |
― |
継続入所の場合 |
|
4 |
就労証明書(129キロバイト/PDF) 就労証明書 (32キロバイト/Excel) |
父母それぞれ必要です。 |
|
|
5 |
保育を必要とする理由書(兼誓約書)(73キロバイト/PDF) |
就労以外の理由で保育を希望する場合 |
|
|
6 |
家庭調査票(57キロバイト/PDF) |
|
|
|
7 |
保育料連帯納付誓約書(79.1キロバイト/PDF) |
― |
|
|
8 |
多子世帯保育料軽減同意書(122キロバイト/PDF) |
- |
|
|
9 |
第3子以降保育料無料化申請書(131キロバイト/PDF) |
|
こちらもご覧ください 外部リンク:内閣府HP – 子ども・子育て支援新制度
お問い合わせ先
こども課 保育係 TEL(0995)23-1311(代表)
災害時における保育施設等の対応ガイドラインを策定しました。
伊佐市では、台風や大雨等の自然災害発生時の保育施設等の対応について、児童や保育従事者の生命と身体の安全を守るために緊急を要する判断が必要になることから、市内で避難情報が発令された場合の対応ガイドラインを策定しました。つきましては、保護者の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
当ガイドラインにつきましては、令和7年4月に策定しております。災害時に備えて内容の確認をお願いいたします。
放課後児童クラブについて
放課後健全育成事業(放課後児童クラブ)とは?
学校の授業終了後及び土曜日等に保護者が就労などで昼間に保育できない小学校に通う子どもたちに、適切な遊び及び生活の場を与え、児童の健全な育成を図ることを目的とし、放課後児童支援員が放課後児童クラブにおける休息、遊び、自主的な学習、おやつ、文化的行事等を含む子どもの遊び及び生活の全般を通じた育成支援を行います。
対象者
小学生1年生から6年生で、昼間、保護者が就労等で保育できない状況である児童。
仕事だけでなく、疾病、出産、障害、介護、看護、就学、被災も含みます。ただし、求職中や内職の方は、児童の帰宅時間帯に自宅で保育が可能ですので利用でできません。
放課後児童クラブ所在地一覧
|
学校区 |
クラブ名(実施場所) |
電話番号 |
学校区 |
クラブ名(実施場所) |
電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
|
大口 |
ふれあい児童クラブ (みどり認定こども園内で実施) |
22-2611 |
大口 |
あゆみ児童クラブ (あゆみ未来こども園内で実施) |
22-5473 |
|
大口東 |
大口東児童クラブ (大口東小学校内で実施) |
22-8861 |
牛尾 |
牛尾児童クラブ (牛尾小学校内で実施) |
22-3110 |
|
山野 |
山野児童クラブ (山野小学校内で実施) |
22-9346 |
平出水 |
平出水児童クラブ (平出水小学校内で実施) |
22-2540 |
|
羽月 |
羽月児童クラブ (羽月小学校内で実施) |
22-5347 |
羽月西 |
羽月西児童クラブ (羽月西小学校内で実施) |
28-2111 |
|
曽木 針持 |
曽木児童クラブ (曽木小学校内で実施) |
25-2155 |
本城 |
本城児童クラブ (旧本城保育園内で実施) |
080-1539-6703 |
|
湯之尾 |
湯之尾児童クラブ (湯之尾校区集会施設で実施) |
26-0640 |
菱刈 |
勝蓮寺児童クラブ (旧慈光保育園で実施) |
26-2145 |
|
田中 |
田中児童クラブ (田中小学校隣接地で実施) |
26-1016 |
|||
|
【留意事項】
|
|||||
○受付場所 こども課子育て支援係(大口庁舎)
地域総務課市民窓口係(菱刈庁舎)
各放課後児童クラブ
○申込に必要なもの 利用申請書、証明書(児童クラブ用)、利用に関する同意書ほか
・利用申請書
・利用申請書(記載例)
・就労証明書
・就労証明書(記載例)
・保育を必要とする理由書
・利用に関する同意書
※申請書類は、こども課(大口庁舎)・地域総務課(菱刈庁舎)及び各児童クラブにもあります。
※保育ができない理由によって、自営業、農業(確定申告等の写し)、出産(母子手帳の写し)、保護者の疾病、障害・病人の介護・看護(診断書等の写し)、就学・技能習得中(在学証明書等)の添付書類が必要です。詳細は申込の案内をご覧ください。
※利用希望児童に弟妹がいて、当該年度の保育園等申込み時に就労証明書等を提出した世帯については、就労証明書等を提出する必要はありません。申込時にその旨お申し出ください。
※就労証明書を提出する(した)方は、保育を必要とする理由書の提出は不要です。
※移行支援シートをお持ちの場合は、写しの提出をお願いします。
移行支援シートとは…
小学校入学にあたり、生活面等で支援や配慮が必要な子どもの情報を保育園等から小学校への提出した文書になります。
放課後児童クラブ保護者負担金軽減事業
放課後児童クラブを利用した保護者負担金額の一部を軽減する制度があります。
詳細、様式等についてはこちら▶▶放課後児童クラブ保護者負担金軽減事業補助金
お問い合わせ
こども課 子育て支援係 TEL(0995)23-1311(代表)
児童手当等について
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として児童手当が支給されます。
1.児童手当等の支給要件
- 児童手当等は、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
- 離婚協議中の場合、児童と実際に同居して養育している父又は母に支給されます。
- 児童養護施設に入所している場合や里親等に委託されている場合の児童については、施設の設置者や里親等に支給されます。
- 短期留学中の場合等を除き、国内に居住していない児童には支給されません。
- 父母が海外に住んでいるが児童が国内にいる場合は、児童を日本国内で療育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給されます。
2.認定請求手続きについて
- 出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合は、市役所窓口で認定請求の手続きが必要です。
- 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
出生・転入から15日以内に請求手続が必要です。
※手続が遅れると、遅れた月分の手当はさかのぼって支給されませんのでご注意ください。
公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が至急されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に市役所窓口と勤務先に届出・申請を行ってください。
・公務員になった場合(受給消滅)
・退職等により、公務員でなくなった場合(受給認定)
手続に必要なもの
- 申請者名義の預金通帳の写し
- 申請者の健康保険証の写し
- 申請者(受給者)・配偶者・大学生年代・18歳以下の別居監護対象児童の個人番号がわかるもの
その他、状況に応じて住民票等の提出が必要となります。
3.支給月額(児童1人につき次の月額が支給されます。)
| 0歳~3歳未満 |
(第1子・第2子)15,000円 (第3子以降)30,000円 |
|---|---|
| 3歳~高校生年代まで |
(第1子・第2子)10,000円 (第3子以降)30,000円 |
※第3子以降の数え方は、親等に経済的負担がある22歳到達最初の3月31日(大学生年代)までの子から数えます。
※大学生年代の子が、親等から日常生活の世話及び必要な保護をしてもらい生活費の相当部分を負担してもらっている場合は経済的負担と言えます。子が就職し、独立して生計を営んでいる場合は経済的負担とは言えないため、児童手当の計算上の第1子としては数えません。
(例)19歳(養育している)、16歳、10歳、5歳の4人の児童を養育している世帯の場合
22歳以下の児童は4人で、19歳が第1子、支給対象となる16歳が第2子(支給額10,000円)、10歳が第3子(支給額30,000円)、5歳が第4子(支給額30,000円)となります。
※第1子・2子が年度途中で3歳になる場合、誕生月の翌月分の手当から減額となります。
(例)11月20日生まれの第1子又は2子が3歳になった場合
誕生月の11月分までは15,000円、翌月の12月分からは10,000円に減額となります。
4.支給期間及び支払時期
児童が18歳到達後の最初の3月分まで支給されます。
下記のとおり年6回、2か月分を、原則として口座振込で支給します。
- 4月15日(2月・3月分)
- 6月15日(4月・5月分)
- 8月15日(6月・7月分)
- 10月15日(8月・9月分)
- 12月15日(10月・11月分)
- 2月15日(12月・1月分)
※15日が休日の場合、金融機関の前営業日になります。
※振込先の口座は、受給者名義の口座に限ります。(児童や配偶者名義の口座は不可)
5.現況届について
児童手当を受給している方は、6月1日現在で受給者が加入している年金や児童の養育状況等を確認するため、毎年6月中に現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、提出が不要になります。ただし、以下にの方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が伊佐市と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、伊佐市から提出の案件があった方
6.手当受給中の注意事項
以下の変更事項があった時は、こども課に届出てください。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出も含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わった時(受給者が公務員になったときを含む)
6.離婚協議中の受給者が離婚したとき
7.国内で児童を養育している者として、海外住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
児童手当に関するお問い合わせ
- 大口庁舎こども課子育て支援係 (電話:23-1311 内線:1220)
児童扶養手当
父母の離婚・父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、手当を支給する制度です。
1.手当の支給対象
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、重度又は中度の障がいがある場合は20歳未満)を監護している父(母)、または父母にかわってその児童を養育している方が対象となります。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が法に定める程度の障がいの状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)に1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 上記以外で父母が明らかでない児童
2.手当の支払い
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
奇数月(1・3・5・7・9・11月)の年6回、各月とも11日に前月分までを指定された金融機関の受給者口座に振り込みます。
※ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の金融機関の前営業日になります。
3.手当の月額(令和7年4月分以降)
| 全額支給 | 46,690円 |
|---|---|
| 一部支給 | 11,010円~46,680円 |
上記は、対象児童が第1子の場合で、第2子目以降の場合は上記金額に5,520円~11,030円が加算されます。
なお、一部支給額は所得に応じて異なります。
4.所得制限
手当を受けようとする人、手当を受けようとする人と生計を同じくする扶養義務者、及び配偶者の前年所得が次の表の扶養親族数による所得限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
所得制限限度額表(令和6年11月分以降)
| 扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者等 | |
|---|---|---|---|
| 全額支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
| 1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
| 2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
| 3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
5.手当支給に必要な手続き
手続きには、戸籍謄本や印鑑、金融機関の口座のわかるものなどが必要となりますが、その他にも提出が必要となる場合がありますので、市の担当課窓口で確認したうえで準備してください。
詳しくは、下記担当課窓口までお問い合わせください。
お問い合わせ
- こども課 子育て支援係 電話0995-23-1311(内線1217)
6.注意事項
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失の手続きをしてください。届出をしないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
- 手当を受けている父又は母が婚姻したとき(内縁関係、同居などの婚姻の届をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の場合も含みます。)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
- 遺棄されていた児童の父又は母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
- 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含みます。)
- 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくするようになったとき(母の拘禁が解除された場合を含みます。)
- その他受給要件に該当しなくなったとき
(注)公的年金や遺族補償等を受けることができるようになったときは、年金等の額によって手当の全部又は一部が支給されなくなりますので、必ずお手続きください。
特別児童扶養手当について
精神や身体に障がいのある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
対象となる児童
- 20歳未満で、精神または身体に一定以上の障がいがある児童
(障害者手帳を持っていなくても、対象となる場合があります)
手当月額(障がい児1人につき次の月額が支給されます。)
- 1級 56,800円 (令和7年4月改定)
- 2級 37,830円 (令和7年4月改定)
支払時期
- 毎年 4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)
◎ 所得制限により、一定以上の所得がある場合には支給されません。
手続きに必要なもの
- 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
- 所定の診断書
- 身体障害者手帳、療育手帳の写し(該当の場合)
- 請求者名義の通帳の写し
- 請求者と対象児童等の個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの
※ この他、必要に応じて所得証明書等の提出が必要となります。
特別児童扶養手当に関するお問い合わせ
- 大口庁舎 こども課子育て支援係(電話:23-1311 内線:1217)
伊佐市子ども医療費給付事業
子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、子どもの健康の保持増進を図るために、病気等で通院・入院した際支払った保険診療による医療費を助成します。県内の医療機関に限り保険診療による窓口負担の必要はありません。
対象となる医療費
医療機関等での外来や入院、処方箋で調剤した薬代等、保険適用分の医療費。ただし、次のものは対象となりません。
- 保険適用外の食事療養費、高額療養費、付加給付、インフルエンザ等の予防接種、健康診断、診断書等の費用
- 学校等でのケガの治療費や薬代は、学校等で加入している「日本スポーツ振興センター」の災害共済給付制度の対象です。学校等への請求になり、子ども医療費給付受給資格者証は使えません。
給付対象の子ども・給付対象者
給付対象の子ども
次の要件を全て満たす子どもが対象です。(すでに他の医療費助成を受けている場合を除く。)
- 生活保護世帯を除く「高校生年代」までが給付対象
※高校生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで - 伊佐市に住所を有する子どもまたは、伊佐市に住所を有する者に現に監護されている子ども
注)重度心身障がい者医療費助成受給資格者、ひとり親家庭医療費受給資格者も対象となります。ただし、受給資格者証を同時に使用することはできません。
給付対象者
子ども医療費の助成の対象になる者は、次のいずれかに該当する方。
- 給付対象の子どもを現に監護している者
- 自ら医療費を負担している給付対象の子ども
給付を受けるには
子ども医療費給付受給資格者登録が必要です。
子どもの出生・転入等がある際には、大口庁舎こども課・菱刈庁舎地域総務課で受給資格者の登録申請を行い、受給資格者証(みず色)の交付を受けてください。
- 受給資格者登録申請書
※印刷される際はA4用紙1枚に集約印刷をお願いいたします。 - 受給資格者登録申請書(記入例)
交付後に住所や保険証等の変更があった際には、こども課又は地域総務課で変更届を行ってください。
子ども医療費受給資格者の登録に必要なもの
- 対象の子どもの保険情報がわかるもの(資格確認書、マイナンバーカード等)
- 保護者の振込口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
- 保護者のマイナンバーがわかるもの(伊佐市に住所がある人は不要)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)
保険診療分に係る助成方法
県内の医療機関等で受診した場合
【現物給付方式・窓口負担なし】
県内の医療機関等受診に限り窓口で受給資格者証(みず色)と、資格確認証やマイナンバーカード等を提示することで、窓口負担の必要はありません。(保険適用外の費用については支払いが必要です)。
県外で受診した場合または県内の医療機関等で受給資格者証(みず色)を提示せずに受診した場合
【償還払い方式】
申請医療機関などで一部負担金を支払い後、大口庁舎こども課・菱刈庁舎地域総務課に支給申請書および領収書を提出してください。
※加入されている保険からの高額療養費や付加給付がある場合は、その額を控除した額を助成します。
※医療費の支給申請書に領収書を添付できないときは、医療機関等の証明で申請することができます。医療機関等の証明料は、医療機関等によって異なり、証明料が発生した際には、1件につき50円を助成します。
※領収書は受診者名、診療日、保険点数、保険診療の自己負担額・領収印、医療機関名が記載されたものに限る。レシートは不可。治療用の補装具を制作した場合は、こども課窓口で、医証(医療機関等から発行)・装具の領収書・支給決定通知書(医療保険者から発行)を助成金支給申請書に添付し提出してください。
※原則申請書は、医療機関等を受診した翌月から6か月以内に提出ください。
支払いについて
県内の医療機関等は、現物給付。県外の医療機関等は、償還払い。
助成金の支払いは、登録口座への振込になります。振込日は、毎月月末です。
※ 振込は、診療月の2か月後以降になります。
こども医療費についての問い合わせ
大口庁舎 こども課子育て支援係
電話:0995-23-1328(直通)
ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図るために、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成する制度です。
1.助成の対象となる方
- ひとり親家庭の父または母とその児童(18歳到達後最後の3月31日まで。ただし、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで。)
- 父母のいない児童
- 父または母に障がいがある場合は、障がいのある父母の配偶者とその児童
2.所得制限
助成を希望される方やその世帯の所得状況により、助成の対象とならない場合があります。
3.助成額
医療機関にかかった医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。ただし、加入保険から高額医療費や付加給付金の給付がある場合は、その額を差し引いた額となります。
4.受給資格の取得
助成を受けるためには、事前に受給資格者証の交付申請の手続きが必要となります。なお、申請に必要な書類等については、市の担当窓口で確認したうえで準備してください。
5.助成金の申請
助成金を受けるためには、受診した医療費について「ひとり親家庭医療費助成申請書」に必要事項を記入し、領収書を添付するか、領収書がない場合は医療機関等で証明を受けた後、提出してください。なお、原則申請書は、医療機関を受診した翌月から6か月以内に提出してください。
- ひとり親医療費助成申請書(様式) (PDF)
- ひとり親医療費助成申請書(様式) (Word)
- ひとり親医療費助成申請書(記載例) (PDF)
詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。
お問い合わせ
- こども課 子育て支援係 電話0995-23-1311(内線1217)
高等職業訓練促進給付金等
母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格にかかる養成訓練の受講期間について「高等職業訓練促進給付金」及び「高等職業訓練修了支援給付金」を支給します。
※申請にあたっては、事前相談が必要です。お早めにご相談ください。
1.対象者
以下の要件を満たす方
- 児童扶養手当を受給している方、または同等の所得水準にある方
- 学校等の養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業・育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 過去にこの訓練促進給付金の支給を受けたことがないこと
※求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、この高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けている場合は対象となりません。
2.対象資格
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師など
3.支給期間
高等職業訓練促進給付金
修業期間のうち上限4年
高等職業訓練修了支援給付金
養成機関のカリキュラムを修了した場合に対象となります。
4.支給額
高等職業訓練促進給付金
市民税非課税世帯:月額100,000円(修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円)
市民税課税世帯:月額70,500円(修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)
高等職業訓練修了支援給付金
市民税非課税世帯:50,000円
市民税課税世帯:25,000円
5.手続きの方法
手続きは、修業を開始した日以後に行うことになります。必要書類等、詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
- こども課 子育て支援係 電話0995-23-1311(内線1217)
自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援するため、指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合に受講料の一部を助成します。
※申請にあたっては、事前相談が必要です。お早めにご相談ください。
1.対象者
以下の要件を満たす方
- 児童扶養手当を受給している方、または同等の所得水準にある方
- 受講しようとする講座が、適職に就くために必要であると認められること
- 過去にこの訓練給付金の支給を受けたことがないこと
2.対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』をご覧ください。
3.支給額
- 一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金の支給を受け取ることができない方
対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円) - 専門実践教育訓練給付金の支給を受け取ることができない方
対象講座の受講料6割相当額。6割相当額が修学年数に20万円をかけた額を超える場合は、修学年数に20万円かけた額(上限80万円) - 教育訓練給付金(一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金)の支給を受けることができる方
1.~2.に定める額から雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額
※いずれの場合も、12,000円を超えない場合は支給しません。
4.手続きの方法
受講しようとする講座を給付対象の教育訓練とするための事前申請をする必要があります。必要書類等、詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
- こども課 子育て支援係 電話0995-23-1311(内線1217)
母子(父子)(寡婦)福祉資金貸付事業
配偶者のない人で現に20歳未満の児童を扶養している人又はその扶養している児童等、寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子に対し、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するための必要な資金の貸付を行います。なお、貸付は県が実施します。
1.貸付を受けられる人
- 配偶者のない人で現に20歳未満の児童を扶養している人
- 配偶者のない人が扶養している児童等
- 父子のない児童
- 寡婦
- 40歳以上の配偶者のない女子で母子家庭の母及び寡婦以外のもの(所得制限有)
- 母子・父子福祉団体
2.資金の種類
使途に応じて12種類の資金があります。資金の種別ごとに、貸付額、償還期間等が異なります。
詳しくは「母子(父子)(寡婦)福祉資金貸付一覧表」をご覧ください。
3.貸付の手続き
- 貸付に際し、申請書や住民票、戸籍謄本、印鑑証明書などの提出が必要となります。
※伊佐市が窓口となり、県が審査(姶良・伊佐地域振興局の専門相談員と面接あり)、決定します。
※申請から貸付の可否決定までに時間を要しますので、お早めにご相談ください。
特に「就学支度」資金の場合は、12月頃までにはご相談ください。
詳しくは、下記担当課窓口までお問い合わせください。
お問い合わせ
- こども課 子育て支援係 電話0995-23-1311(内線1217)
奨学金を受けたいときは
奨学金とは、経済的な理由で高等学校等での修学が困難な学生を援助するために、無利子で市が貸し出すものです。
1 対象
市内に住民票のある人の子どもで、高校、高専、専門学校、短大、大学等に在学・進学(予定)し、学習意欲があり、学資の支払いが困難と認められる者
2 貸付金額
①高等学校など 2万円以内(月額)
②大学など 5万円以内(月額)
③入学準備金 10万円以内
※すべて無利子です。
3 貸付期間
当該学校の正規の最短修業期間中
4 書類提出先
菱刈庁舎2階 教育委員会教育総務課
5 奨学生の決定
奨学生選考委員会に諮って決定
6 返還
①の場合…6年以内
②の場合…12年以内
③の場合…5年以内
※卒業後1年据置
7 その他
卒業後、伊佐市に居住し、かつ就業すれば、奨学金の返還を免除する制度があります。(令和5年度貸与者から対象となる)
※ 奨学生願書及び奨学生推薦調書は、菱刈庁舎教育委員会教育総務課においてあります。また、このページからダウンロードもできます。
奨学生のみなさまへ
その他の諸届について
伊佐市奨学生条例施行規則第8条の規定により、以下の変更が生じた場合は届け出をしなければなりません。
以下の届け出がない場合、市からの重要な通知が届かなくなり、滞納の原因の一つになりますので、必ず手続きを行ってください。
1 転居・改氏名・転籍・勤務先変更について
住所、氏名、電話番号、本籍地、勤務先に変更があった場合は、変更届を提出してください。
2 連帯保証人変更届について
連帯保証人死亡など、連帯保証人を変更すべき事由が生じた場合は、「連帯保証人変更届」を新連帯保証人の印鑑登録証明書を添付の上、提出してください。
3 その他
諸手続き等で不明な点がありましたら、市へ連絡してください。
様式第4号の1(第8条関係)異動届
様式第4号の2(第8条関係)転居、改氏名、転籍等変更届
様式第4号の3(第8条関係)連帯保証人変更届
【問い合わせ先】菱刈庁舎 教育委員会教育総務課 総務係 (電話:26-1512)
就学援助制度
伊佐市では、小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施のために、就学援助費制度を実施しています。
就学援助費制度とは
学校教育法に基づき、経済的な理由によって子を就学させることが困難と認められる方に対して就学に必要な費用を援助することにより、円滑な義務教育を受けていただくための制度です。
援助が受けられる方
伊佐市内に住所を有し、市立の小・中学校に在学する児童生徒または入学予定者の保護者で、教育委員会が定めた基準を満たす方です。
援助の種類
援助する費用の種類は次のとおりです。(金額については教育委員会が別に定めています。)
- 学用品費
- 通学用品費
- 新入学児童生徒学用品費(入学前に入学準備金を受給している場合は対象外)
- 修学旅行費
- 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
- 学校給食費
- 医療費(学校保健安全法に定められた疾病)
- オンライン学習通信費
小学校入学予定者については、新入学児童生徒学用品費(入学準備金)のみ援助します。
支給の方法
学期末ごとに保護者の指定した口座へ振り込みます。
なお、医療費については利用された医療機関へ教育委員会が直接支払います。
申し込みについて
- 申請の受付は、各学校で行っています。
- 小学校入学予定者の入学準備金の申請は、教育委員会学校教育課でも受け付けます。
- 就学援助の認定については、教育委員会で審査し決定しますが、認定には基準があり、申請をしても認定されない場合もあります。
- 認定審査は毎年実施しますので、認定をされている世帯であっても毎年度申請が必要です。
問い合せ先
伊佐市教育委員会学校教育課学事係
電話:0995-23-1311(代表) 内線2201・2205
かごしま子育て支援パスポート事業
地域全体で子育て家庭を支援するため「かごしま子育て支援パスポート事業」に取り組んでいます。
- 鹿児島県作成のチラシ(3メガバイト/PDF)
- 伊佐市作成のチラシ(令和3年2月5日現在)(532キロバイト/PDF)
対象者
鹿児島県内に在住する妊娠中の方及び18歳未満の子どもがいる世帯
※ 子育て世帯であれば1人1枚発行できます。(ただし、18歳未満のお子さんは除きます。)
支援内容
子育て支援パスポートを協賛店で提示されますと割引や優待サービスを受けることができます。このサービスは協賛店の善意によるものです。
- 伊佐市内の協賛店舗はこちら(令和3年2月5日現在)(180キロバイト/PDF)
- 伊佐市以外の協賛店舗について、かごしま子育て支援パスポート専用サイトにてご確認ください。
パスポートの取得方法
かごしま子育て支援パスポート専用サイトで「パスポート新規登録」を行い、スマートフォンにパスポート画像を保存してください。
協賛店を募集しています
未来を担う子どもたちの成長や子育てを支援していただける協賛店を募集しています。こども課でお申し込みをお願いします。
かごしま子育て支援パスポート専用サイトの「協賛店舗の新規申込」ページで利用者登録をお願いします。
お問い合わせ先
こども課子育て支援係 電話 0995-23-1311
- こんな時には?